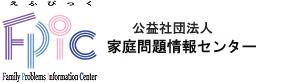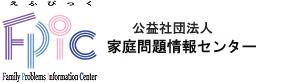第1 ハーグ条約と子どもの利益
2005年、弁護士である父親が登校途中の小学3年の娘を駅の改札口から連れ去り、執行猶予付きながら懲役刑が言い渡された事件、
2009年、日米の二重国籍を有する医学博士で会社経営者である父親が、
子どもを母親から奪取してアメリカ領事館に逃げ込もうとして逮捕された事件、
いずれも当時新聞やテレビを賑わした子どもの連去り事件です。これらは氷山の一角に過ぎず、国際結婚の増加に伴い、
子どもの奪合いや国外への連去りの問題が深刻さを増しています。
国際結婚の破綻の際に発生する子どもの国外への連去りに対して、欧米の多くの国は、
オランダのハーグ国際私法会議で1980年に署名され、1983年に発効した「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(仮訳)」、
いわゆるハーグ条約を批准しています。加盟国では、他方の親の了解なく子どもを国外に連れ去った場合には、
連れ去った親の居住国が送還拒否の判断をしない限り、子どもをいったん常居住地に強制的に送還し、
送還先の国で監護者が決定されることになっています。未加盟の日本に対して欧米諸国は再三の加盟要請を行い、
2010年9月には、アメリカ下院が日本を非難する決議まで行いました。ハーグ条約は家事法制に対する黒船などといわれ、
政府も「前向きの検討をする」と回答しています。
アジアでは、多くの国が加盟していません。ハーグ条約は、もともと暴力的に子どもを国外へ連れ去る父親を想定して作られた
条約だったようですが、実際には、連去りの約7割が母親という想定外の事態が起きています。理由は、
アジア人や少数民族の母親が、欧米人の父親からのDVを伴う人種的、経済的、性的な差別を受け、
母子で母国へ逃げのびる事例が少なくないからです。ハーグ条約は、原状回復、
すなわち不当に親権を侵された側の親の権利の回復を最優先し、子どもの福祉が検討されるのは監護者を決める段階になってからです。
渡航費用等の用意ができない母親は、子どもといっしょに常居住地へ戻る必要はありませんが、
これまでに、子どもを戻して監護者になれた親は2割程度であり、あらたに決まった監護者には面会交流に応じる義務はありますが、
強制されることはありません。欧米に比べて社会、経済的条件に格差のあるアジアの国々には、
加盟のメリットは感じられないことでしょう。
日本には欧米基準の採用が迫られています。ハーグ条約は、後の1985年に成立した、
子どもの利益の最優先を謳っている「児童の権利に関する条約」との整合性が課題になっています。
批准した場合には、親同士の権利関係の調整が主眼であるハーグ条約のもとで、子どもの権利、
利益はどのように守られていくのでしょうか。
ハーグ条約による連戻しは、一方の親の国に返すのであって、DVの父親の家に戻すわけではない、監護者が決まるまでは、
里親、施設等で適切な監護を行うので子どもの福祉が害される心配はないと説明されます。衣食住への配慮に心配はないでしょうが、
子どもは物ではありません。親の連戻し要求の正義が、子どもを国を越えて移動させた上に、他人や施設に預けてまで、
優先して守るべき価値であるとするには、どこか釈然としないものを感じます。
FPICでも、面会交流の援助の中で、奪取が繰り返された子どもの情緒不安定、
両親から引き離されて児童相談所の一時保護を経験した子どもの親子の再統合の難しさ、
シェルターに駆け込んで、所在を隠したり偽名を使わされたりした子どもの自尊心の損傷等に遭遇します。子どもに負担をかけた
居所の移動は、母親が実家に連れ帰った子どもとは同列に論じることのできない深い心の傷を子どもに負わせています。
連戻しを命ずる国は、子どもの心の安全と安心を十分斟酌して、真に適正妥当な判断をすることが期待されます。
また、法的枠組みによって連戻しや監護者を決めるとしても、非監護者と子どもの面会交流及びその早期開始が保証されるような
準備がなければ、決定はあらたな子どもの引離しに手を貸したことになってしまいます。アメリカのように、別居が始まったら、
他の案件に先駆けて、2か月以内にまず面会交流の取決めをするとか、高葛藤事案の面会交流を支援する制度を構築するなど、
手続上、制度上の体制整備が焦眉の急になっているといえます。平成22年秋に、
法務省は「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究」に着手しました。
面会交流支援と比較法調査を内容とした委託研究です。今後の動きに期待と関心を持って注目していきたいと思います。
FPICが関与している面会交流の援助事例では、親子の断絶の長期化を避けるために、離婚調停や訴訟の途中から、
面会交流の合意形成を先行させ、面会交流を実施しながら離婚の調停や訴訟を進める事例が最近増えています。
第2 共同親権・面会交流と子の最善の利益
平成8年の民法(離婚法)改正が要綱案のまま凍結されてからも、家族法分野の関係者の間では、
親子法を含めた家族法のあるべき姿を求めて検討が重ねられています。ハーグ条約批准への要請の動きと歩調を合わせるように、
共同親権、子どもの連去り禁止、面会交流の法律上の明文化を求める民間の動きも活発になり、法案作成、
議員立法への試みなどのあることが報じられています。
平成22年末には法制審議会から「家事事件手続に関する要綱案」が公表され、子の監護に関する処分の審判に関する条項の中で、
「面会及びその他の交流」という用語が使われています。離婚に対する破綻主義を前提に、法律上の規定がどうあれ、
離婚が理由で親子の縁が切れることを防止しようとする意識は確実に強まっていることが感じられます。
しかし、営々として面会交流の援助を続けてきたFPICとしては、
基本的枠組さえ見えない法整備の遅い歩みに苛立ちがないとはいえません。親権ひとつをとっても、妥当な用語の選択、
親権の具体的な設計内容(現行法上の問題点の整理と改正方向、親権・監護権の原則、
共同すべき事項等)の議論が熟しているとはいえない状況です。面会交流でいえば、両親は共に義務者であり、
権利者は子どもであることが実態において実現するような、子どもの利益を優先する観点からの議論を尽くして
立法化を急いでほしいところです。
日本での面会交流を子の最善の利益中心で考えるなら、子どもの日常生活の実情を尊重した運用が必要です。
親の迎えなしには子どもだけの帰宅を認めない欧米のような自己責任、家族中心の社会と、地域社会が消滅したといわれながらも、
児童見守り隊の地域の老人たちの送迎を受けたり、集団登下校をしたりする子どものいる日本社会との違いを認識する必要があります。
地域の学童クラブ、野球・サッカーチーム、学年が上がれば部活動、おけいこごと、塾なども、
欠席すれば子どもは居場所を失いかねません。子どもの家族外の人的ネットワークへの配慮が不可欠です。親の要求で、
子どもをドッジボールのように頻繁にやりとりすることは、決して子どもの要求に沿っていないことを知っておいてほしいものです。
連去り禁止や子が親に会う権利を明文化することは必要でしょう。それと同様に、あるいはそれ以上に、
子どもの成長にとって意味のあることは、面会交流をいっときの熱情的交流に終わらせることなく、
生きる楽しさを伝えてくれる親との交流が、細くても切れずに長く継続することです。日本の社会風土や子どもの年齢、
生活習慣に見合った継続可能な面会交流を、個々に辛抱強く模索していくことが重要ではないかと考えます。
第3 児童虐待防止法等の見直しの進歩と限界
平成12年に成立した「児童虐待防止等に関する法律」(児童虐待防止法)は、
安全のための立入強化を盛り込んだ平成19年の改正法の中に、平成20年の施行後3年以内に更に必要な改正を行うことが
決められていました。そのための検討結果が平成23年初めに「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する要綱案」
として公表され、民法、児童福祉法等の関連法の一部改正も含め、平成23年の通常国会に上程される見込みです。
主たる改正点は、親権の規定についての改正ですが、そのひとつは、監護、教育の権利と義務の行使を、
「子の利益のため」であることを初めて明文化したことです。これは評価されてよい進歩ですが、親の懲戒権は、
将来その存否を検討するということで、削除されませんでした。児童虐待の事例で親が再々抗弁の理由にするのも、
「子のため、しつけのため」であることを考えると、「子の利益のために必要な範囲で」という懲戒権の制約が、
現実にどのような歯止め効果をもたらすのか、いささか疑問に思われます。
他の大きな改正点は、親権の喪失等の条項に、親権の一時停止(最長2年)の制度が新設されたことです。
これまでは期限のない親権喪失の規定のみであったため、対応が慎重になり適用事例は年間20件程度にしか過ぎませんでした。
親権の一時停止は虐待に迅速、柔軟に対応して、早期再統合を目指しうる事例を対象とするための改正です。
早期再統合を目指す制度の趣旨にかんがみ、2年での親元復帰が困難な場合は、更新ではなく再度の申立が必要となります。
新聞報道によれば、要望の強かった現場からは歓迎されているとのことですが、3年を要望していたという現場にとっては、
2年という課題を負わされたことになります。初期には親との対応が、終期には親と子の再統合が、大きな課題になるはずです。
法制審議会と分担連携して、社会保障審議会の親権のあり方に関する専門委員会も、
平成23年1月に「児童の権利利益を擁護するための方策について」という報告を出していますが、その中のひとつに、
児童福祉法の一時保護の見直しがあります。日本の一時保護期間は2か月であり、諸外国から見ると長いのです。
一時保護の期間中は、子どもは夫婦の争いに巻き込まれないようにとの理由で、
両親とも面接を禁じられます。見直しの結果は期間に変更はなく、期間延長のチェック方法が明示されただけでした。
延長に対する親の同意がなければ児童福祉審議会に意見を聞くこととし、司法審査にかけるとの意見は採用されていません。
一時保護について、2か月という諸外国に比べて長い保護期間の妥当性を、
一時保護の後の面会交流の事例を紹介しながら考えてみたいと思います。父親が母親宅前で母子の外出を待ちうけ、
自力で子どもを取り戻そうとして双方暴力沙汰になり、仲裁に入った警察官の説得も効なく、
警察官の勧めで両親が一時保護を選択しました。父親は、「あのときは、
相手に取られるくらいなら施設で面倒を見てもらう方がましだと思った。
親権を取れないんだったら子どもに辛い思いをさせただけだったと、いまは反省している」といっていました。
母親が監護者指定を受け、施設への訪問面会、職員の家庭訪問、試行的自宅宿泊等所定の手続きを経て、
ようやく子どもを引き取ったときには、子どもは笑顔も甘えも示さず攻撃的になっており、
その変貌ぶりに途方にくれたと母親は訴えていました。2歳児が、突然母親から隔離されて2か月もの期間を施設で過ごした後の、
母子の再統合、父親との面会交流の難しさを経験した事例です。裁判所はかなり急いで監護者を決めたようですが、
引き取れたのは2か月後です。措置期間の原則は2か月でも、この事例のように虐待のない年少幼児のためには、
もう少し柔軟な運用を望みたいものです。
第4 終わりに
親権停止にしても、一時保護にしても、緊急避難的な措置であるとはいえ、子どもが被る被害が皆無であることはあり得ないでしょう。
そのようなとき、純粋に子どもの立場に立って、子の権利、
子の利益の擁護に当たる役割(子ども代理人制度)の必要性が主張されています。
ただ、臨床場面で、常に子ども代理人という自覚をもって子ども支援を行ってきた私たちとしては、
期待される役割が法律家による法手続に限定されるのが制度設計として適切であるのかどうか、
今後の議論の深まりを期待したいところです。当面は、子どもの利益について臨床家としての鋭敏な感覚を養いながら、
FPICは、責任ある発言、発信を続けたいと考えています。
|