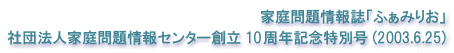

1 はじめに
最近、本屋で漠然と新書版の棚を見ていましたら『変貌する子ども世界』(本田和子)とか、『子どもという価値』(柏木恵子)(いずれも中公新書)が並んでおり、 20世紀は子どもの時代といわれてスタートしたはずなのに、世紀の後半は子育てが破綻した時代だという立場で書かれていました。 『ふぁみりお』も「いま子どもたちは幸せか」という記事を何回か取り上げ、子どもたちの不幸で、心配な状況を伝えています。一方家族論では、個人の意思をできるだけ尊重し、多様な生活形態を「家族」として認めるべきだとの議論があり、週末だけ一緒に過ごすカップルも、 婚姻届を出さないカップルも、さらに単身者同士が精神的に結ばれているカップルも、皆家族として同等の優遇が受けられるべきだとする主張がありますが、 そうなると「家族」という概念は霧散してしまいます。しかし、現実には、大多数の人々は、生物原理に従って異性とカップルを作り、性愛の結果子が誕生し、 性愛の延長上で生まれてきた子に愛情を注ぎ、一人前に養育する責任を引き受ける形で家族を形成しています。 もちろん、個人の人生には、いろいろな選択肢があってよいのですが、先に述べた個人意思尊重の家族論は、例外的なものを普遍化する誤りだけでなく、 家族が社会から保護される根拠を見失っているように思います。
また、最近の生物学は、生命について次のように教えています。それは、今から何億年か前に「もの」の一部が「自己触媒による自己複製機能」を持つようになり、 それがあるとき膜で囲われて、遺伝子を持った「細胞」となるわけです。その後、細胞が集まって個体となり、種の進化を遂げながら「ひと」に到達するのですが、 その間、細胞は分裂を繰り返しながら連続しているわけです。ところが近代の人たちは、これらの細胞を自分の個体の中に自ら所有しているような感覚でいるのですが、 遺伝子から見れば、人間の個体は、自己複製の便利な運び手ぐらいにしか当たらないのです。われわれが意思とか主体と感じているものは、 コペルニクスの転換以前の天動説の世界にいるようなものかも知れません。
さらに、「ひと」は、二足歩行の関係で産道が狭くなったため、赤ん坊は小さく未熟なうちに生まれてくることになり、 母親と身体的に切り離された後に長い時間をかけて脳を含めた身体各部が発達するようになったと言われています。 そのため、乳児は母なしには生きていけなくなり、一人前になるまでの長期化した子育てを担うシステムとして、父親のいる「家族」が生まれたと考えてよいようです。
このように考えると、一見私事に見える家族には、養育機能という種の進化を支える公的な役割のあることが分かります。 その重要な機能を、家族は、この半世紀の間に、産業の集約化の波に乗って、次々に社会へ放出し、残された育児機能も、あちこちで綻び出しているというのが、 今日の家族問題を考える出発点だと思います。
2 コミュニケーション能力と乳児期の養育環境
最近の思春期の子どもたちが示す不適応行動をみると、他人とこころを交流する能力が低下し、こころの根底にある自分を信じる力の不足が顕在化してきています。 たとえば、同情より自己防衛を優先させる「いじめ」の傍観者にして然り、内面を語れない少年たちの突発的非行にして然りです。 また、摂食障害では、放っておけば死ぬ危険を冒してまで親を振り回さないと満足できない母親不信が根底にあるとの指摘があり、悩みを言葉では語らず、行動で示します。エリクソンがいう基本的信頼や、信頼できる相手と情緒を分かち合う交流能力の基礎が、乳幼児期の養育環境、特に早い時期の母子関係にあることは、 多くの専門家の観察によって明らかにされています。また、この問題に最初に注目したボウルビイやスピッツは、今から約半世紀前に、 何らかの理由で人生の早期に母による養育から切り離された幼児が、しばしば経験の統合能力や言語能力について発達の遅れを示し、 それが後の社会不適応につながることを指摘しています。さらに、その後の研究は、いかに早くから母子が、リズム、音声、 視線などを使って交流しているかを明らかにしていて、ここに「こころ」を分かり合うコミュニケーションの萌芽がみられます。 それだけに、こうした交流が楽しく安定して行われるように、母子関係を支える父親や周囲にいる者の役割もまた重要です。
しかし、最近、子と上手にかかわれないことに悩む親がみられるようになり、 このような母親への援助として「乳幼児母子関係治療」という新しい精神医療の分野が生み出されています。 また、子どもと上手にコミュニケートできないで苛らついた親による児童虐待が、しばしば新聞紙上を賑わしているところですが、 さらに思春期の非行との関連では、少年院に収容された少年の約30%が、親による反復的な身体的虐待を経験していたとの報告があり、 育児環境がいかに危機的な状況にあるかが容易に想像されます。
成長後の交流能力の基礎となる母子の交流経験は、比較的早い段階から父親によって代替できますが、ごく初期の母乳による授乳行動や、 その機会に発せられる言葉掛けなどでは、胎児の時から継続している母子関係の優位性は間違いないところでしょう。
このような乳幼児の養育についての知識は、広く社会で共有する必要があると考えますが、家庭や学校では、 一度も教えられなかったと訴える母親が多いことも事実です。また、とかく論議を呼ぶ三歳児神話の問題も、母親が働くか否かを論じるより、 専業主婦が孤立しないための援助とか、働く母に代わって育児を行う機関の保育の質などの影響を論じることの方が、よほど急務であるといえるでしょう。
3 コミュニケーション能力低下と科学優先の文化
自然科学が重視する客観性は、誰もが検証してみることができることを指していますが、その前提には、観察の対象が規則的、反復的に変化することが必要です。 ところが、人が直接経験する「こころ」のように、本来個別的である現象については、もともと適用することが無理な条件です。 そこで、自然科学を標榜した心理学は、生理現象か動物の行動を研究する学問になってしまい、 こころの問題として大切な愛とか信仰といった内容を扱えない心理学になってしまったと戸川行男教授(故人、私の恩師)は述べています。 そこで、他人の心は類推する以外に触れようがないので、こころを研究するには、自己分析しかないと結論づけています。 私は、こころの機能には、自然科学にない「了解する(分かる)」という重要な手段が備わっていて、 二人の人間の間に「分かった」とか「分かってもらえた」という体験が成立すると、満足感や感激が生じ、それを体験した人びとの意識や行動に変化が生じるという、 きわめて現実的な利益を生むという事実を重要視したいのです。このことは、カウンセリングや精神療法を通じて多くの人が認めるところですが、このようなコミュニケーションの能力は、 人生初期の親子の交流から芽生えるというのが、前項で指摘したところです。そして、「もの」の科学ばかりが尊重される中で、 人は徐々にその能力を失い、マニュアルを頼りに機械を扱うことは上手だが、乳児のこころを読み取ることは苦手な親が現れたというのが私の主張したい点です。
先ほど紹介した『子どもという価値』という本の中で柏木恵子教授は、出産が親の意思で自由にコントロールされるようになった結果、 子に対する親の私物化と支配が強まったと指摘していますが、これも子どもを一種の「もの」と見てしまい、 機械のように扱おうとするところから生じているとも考えられます。
4 バブル経済崩壊後に求められたもの
経済の高度成長期に求められた価値は、こまごましたものを集約して規模を拡大し、経済効率を高めるとともに、品質管理では生産品が均質であることが重視され、 そこで働く人間にも同様のことが求められ、一時は、金太郎飴のようにどこで切っても同じ顔が現れる職場が良いとされるほどでした。ところがバブル崩壊後に量的な追求が困難になり、独自性が尊重されるようになると、一転して働く人にも個性と創造性が要求されるようになりました。 こうなると、「もの」の論理より「こころ」の論理の方が得意であり、今こそ失われた「こころ」を回復するチャンスだと思います。
そこで、その方法ですが、高度成長期の集約化と均一性の原理を象徴するファーストフード文化に対抗する新しい価値観として現れた 「スローフード」の運動に注目したいものです。これは地域の伝統文化を大事にし、小規模生産者を守り、子どもたちに伝統の味と文化を伝え、 手作りを尊重するという文化運動で、この広がりの上で、スローワーク、スローライフが提唱され始めています。 一方、大量生産と競争原理に埋没しているときは、自由と平等だけが強調され、かつては同等に強調されていた友愛という第3の分かち合う価値を忘れ去ってしまうのです。
ここで思い出すのが、霊長類研究家で『家族の起源』を書いた山極寿一さんの指摘です。 それは霊長類に見られる行動で、弱いものが強いものの顔を覗き込むことで食物の分配に預かるのですが、 このとき、分配する側は、大人同士では見ることができなくなくなった笑い声や笑顔を報酬として得ているという観察結果です。 そして、この行動は、母と幼児の間の親密な交渉から発展し、優劣が露呈しない社会行動として浸透したと見ていて、 母子関係→親密性→優劣原理によらない共存へと展開している点に興味を覚えました。 それは、人間という種が弱肉強食に陥らないための重要な機能であることを示唆しているからです。
5 家族を再生するために必要な価値観の転換
最後に、家族の再生について述べてみたいと思います。家族機能の低下の背景には、社会変動の流れがあったわけですが、 これを改めるためには、価値観の転換を図ることが必要で、閉塞感が抱かれている現在こそ、転換の好機ではないかと考えます。そこで、まず必要なことは、働くことと家庭生活との関係を逆転させることではないでしょうか。 すなわち、「働くための休息施設」という家庭観を捨てて、「家族で過ごす楽しみのために働く」という勤労観への転換を図ることです。 次に必要なことは、若い世代の人たちに、家族を持つことや、子を産み育てることへの動機を高めるために、 まず親の世代が、「結婚っていいな、自分もそんな体験をしてみたいな」と我が子に思わせる「楽しい家庭生活」や「仲好し夫婦」のモデルを実践することでしょう。
精神分析医の小此木啓吾教授は、これからの家族は、一つの集団として機能することが難しくなり、独立した個人の集合体としての色彩を強めると考えています。 そのため、現在の家族が、当然そこに備わっているものとして期待する家族像の「Being Family」はすでに過去のものになりかかっていて、 これからは長期休暇のプランや誕生日の楽しみなどを、家族が集まって自分たちで計画し、皆が行動することで作り上げていく家族、 すなわち「Doing Family」への転換が必要であることを『ドゥーイング・ファミリー』(PHP研究所)という本の中で提唱しています。