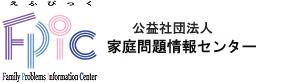
|
||
|
|
||
|
||
FPICの支援による実施のためのルール |
||
親子交流予約における個人情報の取扱いについて |
||
| 本ホームページの内容を無断で転載することを禁じます。 | ||
| Copyright(C)2010 Family Problems Information Center | ||
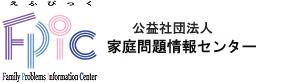
|
||
|
|
||
|
||
FPICの支援による実施のためのルール |
||
親子交流予約における個人情報の取扱いについて |
||
| 本ホームページの内容を無断で転載することを禁じます。 | ||
| Copyright(C)2010 Family Problems Information Center | ||