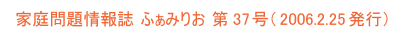|
1 父親として成長するまでの長い旅路
−Aさんの5年間の心の変化−
最初に、Aさんのお話を紹介しましょう。Aさんは、面会交流の初期の混乱、中期のあせり、
そして軌道に乗るまでのすべての過程を経験し、どん底から這い上がった、いわば苦労の達人です。
ここまで到達するのは並大抵のことではありませんし、誰にでもできることではありませんが、
会う側の親としてのあり方を深く考えさせてくれます。
「離婚を求める元妻が、子どもとわたしが会うのを認めるのに3年かかりました。
会うためには、毎月会いたいという要求を年4回に下げ、元妻がお互いの顔を会わせることも連絡を取り合うことも全面的に拒否したため、
FPICの援助を受けることに同意せざるを得ませんでした。
その間、ひどく落ち込んで、生きていることさえ嫌になった時期があり、
何かにすがる思いで寺を訪ね、読経の会に参加しました。
ある日のこと、同年輩の男性が隣り合わせたので、もしかしたら同じようなことで苦しんでいるのではないだろうかと思って声をかけ、
自分のことを話してみました。隣の男性は言いました。『今は会えなくても、あなたのお子さんは元気に暮らしているのですね。
いいですね。わたしの子どもは、こうして菩提を弔ってやるしかないのです』と。
わたしは、目から鱗が落ちる思いでした。
自分ほど不幸で、元妻ほどひどい人間はいないと思って、恨みつらみに押しつぶされそうになっていた自分に気がつきました。
会う回数や時間で争っているより、早く会おう。一期一会の気持ちで、会えたそのときそのときを大切にしようと決めたのです。
3年ぶりに会うときには、子どもがどんな風に受け入れてくれるかとても不安でした。
不安は杞憂に終わりましたが、別れぎわが辛くて涙がとまらず、しばらくは部屋を出ることができませんでした。
FPICの担当者に、今日だけは思い切り泣いてからお帰りなさい、といわれたほどでした。
FPICを利用して2年経ちます。元妻は、初めのうちFPICの担当者が付き添って室内で会うことしか認めず、
プレゼントにも毎回クレームをつけてきました。『会えなくなるよりはまし』と自分をなだめながら、時間を守り、
プレゼントも指示に従いました。2年目に、やっと外で会うことを認めるようになりましたが、
今でも決して望んでいるような会い方になっているわけではありません。でも、子どもたちは元気に育ち、
春からは下の子も小学生です。わたしと会うことをたいへん心待ちにしてくれています。この子どもたちを産んでくれたのは元妻ですし、
元妻のような強い女性と出会わなければ、短気でわがままだった自分はこんなに辛抱強くはなれなかったと思います。
いまでは、元妻に感謝さえしています」
Aさんが、このような苦しい選択をすることができたのは、Aさんがもともとたいへん子煩悩で、
子どもとよく遊んでいたという事実も見逃せません。
「子どもと遊ぶときには、子どもの目線で子どもになって遊ばなくてはだめですよ」とはAさんの名言です。
次に、面会交流の経過を、開始期、中期、安定期に分けて、それぞれの時期のお父さんの声を紹介します。
2 みんな悩んで父になる−それぞれの旅路
(1) 面会交流の開始期
−会えない苛立ちと援助への抵抗−
BさんとFPICとの出会いは、不本意で、消極的な出会いでした。さまざまな抵抗感のために両親間での面会交流に応じられないお母さんが、
Aさんのときと同じように、応じる条件として持ち出したのが「FPICの援助を受ける」ことだったからです。Bさんは、両親だけで面会交流ができるように、
お母さんを指導してくれるならFPICの援助を受けたいといいます。
Cさんは、費用負担と面会場所を限定されることが不服で、まだ面会交流を開始することができません。
養育費や生活費、ときには慰謝料などを支払った上に、援助費用の負担を負わされることの多いお父さんにしてみれば、重ね重ねの出費です。
できれば当事者で、と考えるのは当然です。事実、援助ケースの中には、お母さんも認めている良好な関係の父子がいます。
お母さんさえ決断できれば第3者の介在は必要ないのです。
しかし、残念ながら、一旦焼き付いたお母さんのお父さんに対する不信感や恐怖感は、ときには周囲の過剰な同調によって固定・強化されて、
なかなか拭い去ることができないのが現実です。
BさんやCさんは、子どもには会いたい、でも、自分の子どもに会うのになぜ金を払わなければいけないのか、
なぜ他人に介入されなければいけないのかという、FPICの援助の入り口に立ちはだかるジレンマと戦い始めたところといえるでしょう。
抵抗の強いお母さんとの条件闘争に消耗していくお父さんには、会えるなら少々の窮屈さを我慢してでも早く会いたい、
顔を見たいとは思わないのですか、それとも、希望の条件に合わなければ会うのを断念するのですかと、
優先課題を選択してもらうことが必要になります。
抵抗の強いお父さんがいるかと思えば、次のDさんのように、妻と暮らす子どものことが心配で、
自から相談をもちかけるFPIC頼みの必死のお父さんもいます。
「調停中で別居しています。妻は性格のゆがみが著しく、情緒不安定で、要求がどんどんエスカレートします。
なんとか穏やかに生活してほしいと思って、意向に沿うようにしても、それがまた怒りの原因になったりして、
まるで洗濯機の中で攪拌されているような生活に疲れ果てました。限界を感じて家を出たのですが、
子どもを引き離すと妻はますます不安定になるので、6歳の子どもを置いてきました。子どもに負担がかかっていると思うと心が痛みます。
妻の反応を考えると、こちらからは近づくことも連絡することもできません。
FPICに妻とのパイプ役をお願いする方法で子どもと会うことはできないでしょうか」
見通しの暗さに、藁をもつかむ思いなのでしょう。
(2) 面会交流の中期
−期待どおりに進展しないあせり−
Eさんは、面会交流の援助を受けて1年になります。
「子どもの城、動物園、子ども科学館、交通博物館、
プール、スケート場など、子どもの希望する場所で、FPICの付き添いのもと、毎月3時間の面会を続けてい
ます。限られた時間とはいえ、親子で楽しく過ごせていることには感謝していますが、元妻の祖父母は自由に子どもに会えるのに、
離婚前にはいっしょに暮らし、育ててもらっていたこちらの祖父母と会うことができないのが不満です。
せめて、面会中に遠くから眺めるとか、携帯電話で声だけでも聞かせてやりたいと思うのですが、いけないでしょうか。
子どもから連絡できるように、電話番号を教えてはまずいですか。子どもは今春小学校の1年生になります。
元妻は嫌がるかも知れませんが、入学式には行ってやりたいですね」
Fさんは、3年目になります。
「FPICには、数回の付き添いの後、送迎だけをお願いするようになって、毎月6時間子どもと過ごしています。
父親とでなければ経験できないことを経験させてやりたいと思って、冒険的な遊びもしています。
もう、小学校の最上級生なので、時間を延長したいし、長期休暇には宿泊もさせたい。自分の郷里にも連れて行ってやりたい。
現状固定のままでは、子どもの発達に見合った面会交流とはいえないと思っています」
EさんやFさんはかなり良い父子関係にあります。お母さんからの制約がとれればもっと自由に楽しい時間が過ごせるのにとの思いが、
子どものめざましい成長ぶりにつきあってきたお父さんのあせりを呼び起こすようです。秘密を持たされる子どもの立場や都合への配慮が、
つい希薄になりがちな時期でもあります。
(3) 面会交流の安定期
−新たな親子関係の受け入れと新境地−
Gさんは、面会交流が始まって2年が過ぎました。
仕事の都合で参加できないからといって、面会交流の合間に感想を語ってくれました。
「1年以上のブランクがあって再会した5歳の息子はなかなか打ち解けてくれず、あせっていた時期がありました。
会いに来るのを嫌がっているともいわれました。
元妻の養育態度に原因があるのではないかとか、育て方のせいで発達が遅れているのではないかなどと思って、
元妻への不信や不満をつのらせました。
FPICの担当者には、『子どもは離婚の理由が分からないので、結果として見捨てたお父さんのことを怒っているものです。
子どもの気持ちを察し、詫びるつもりで一心に遊んでやらなければ、子どもは心を開いてくれません。
お母さんの問題というより、お父さんの心の問題ではありませんか』といわれました。
納得したわけではありませんでしたが、汗をかき体を動かして子どもと遊んでみると、子どもは驚くほど活発になり、
大きな笑顔や笑い声が出るようになりました。子どもが求めていたものが分かったような気がして嬉しかったです。
子どもは、今では会うのを楽しみにしてくれています。最近、足が遠のいていたゴルフや飲み会にも行くようになり、
離婚したことも話せるようになりました。メンバーの中にも離婚経験者が何人もいたことがわかりびっくりしました。
離婚の先輩たちから、『そんなことでめげるようではまだまだ甘い』とカツを入れられました。仲間を得て肩の力が抜け、
気持ちも楽になりました。子ども子どもといって、子どものことばかり思いつめていた頃の自分は、視野が狭く自己中心的で、
本当のところでは、子どものためになっていなかったと思います」
かつてのけわしい顔つきからは程遠い、柔和な笑顔のお父さんの言葉です。安定期のお父さんに共通して見受けられる、
新たな境地といえるでしょう。このようなお父さんの変化に出会えたとき、担当者は、担当者冥利ともいえる喜びを味合わせてもらっています。
しかし、ほんとうの安定期とは、子どもが安心して本音をいえる環境を父母が協力して整え、
他人の手を借りることなく面会交流が実行できたときのことを指すのではないかと思います。
自立期とでもいうのがふさわしいでしょう。父母が自立期に到達できたとき、そこには、
子どもによって繋がった新たな関係ができ上がったといえるのではないでしょうか。
3 FPICからお父さんへのお願い
(1) 子どもを板ばさみにしないで
面会交流の現場で、担当者が一番心を痛めていることは、子どもが父母の間で板ばさみになっていることです。
面会交流とは、親が子どもを気づかうもので、子どもが親を気づかうものではありません。
たとえば、持ち帰れば捨てられるかもしれないプレゼントを、受け取らなければお父さんに悪い、そんな子どもの気持ちを、
ぜひ考えてみてください。子どもがお父さんに会いたいのは、物や金ではなく、かわいがってほしい、いっしょに遊んでほしいからなのです。
(2) FPICを上手に活用していただくために
開始期―スムーズな開始のためには、来室の上、FPICの援助内容を理解してから、面会の頻度、場所、費用の負担割合、
FPICの指導助言を受け入れることなどを取り決めて、契約してください。
付き添い援助の場合は、両親の緊張関係を考慮し原則として、両親の自宅では会わない、宿泊はしない、
祖父母を援助の対象としないことになっています。
不安や躊躇が強い場合には、年間契約をする前に、試行的な面会交流の相談にも応じています。
中期―子どもが手許にいるお母さんと、離れて暮らすお父さんでは、痛みの度合いが違います。先を急ぐお父さんのペースでは、
お母さんはついて来られないことを理解する必要があります。もちろん、担当者は、子どもを私物化しているようなお母さんには、
逆の立場を想定してもらい、囲い込みを緩める働きかけを続けています。でも、あまり無理強いすれば、子どもが板ばさみになってしまいます。
初めの1年位は、クレームをつけるより、信頼感を得るために取り決めを守ることが賢明です。
その実績があれば、担当者からのお母さんへの説得的調整も功を奏しやすくなるのです。
安定期―この時期はたいへん長期間になるものと予測してください。付き添い援助が送迎援助にステップアップできれば上首尾です。
両親が顔を合わせることができなければ、この先へ進むことは難しくなりますので、その場合、連絡調整だけを引き受けることはできます。
いずれも平坦な道のりではありませんが、急がず、あせらず、ルールを守って進めるのがコツです。
お父さんと子どもの心の架け橋になれるよう、FPICは応援し続けます。
|