
|
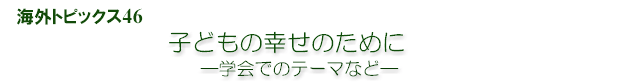
|
|
最近の家族法の主なテーマは、お年寄りや子どもなど家族の中でも弱い立場にある者への配慮が中心になりつつあり、会議でも度々取り上げられています。 2008年9月にウィーンで開催された国際家族法学会(International Society of Family Law)の世界会議には、世界各国から多数の学者や実務家が集まり、 家族の財政(family finances)について討論が行われました。 同年11月には東京で日本家族<社会と法>学会の学術大会が開催され、そこでは特別養子制度を中心にシンポジウムが行われました。 いずれの学会でもそれぞれのテーマのもとに広範な問題を取り上げていますが、中心となるのは特に子の幸せとこれを確保するための制度の問題です。 ここでは、そのうちの二、三を取り上げてみましょう。 |
国際家族法学会(2008.9 ウイーン)本学会では家族の財政(family finances)をテーマに掲げていますが、主眼は家族の連帯のための資源の配分、子の養育費の確保などにあり、それを目指す国の責任と関与、 すなわち制度も論じられました。 全体会議のほか、約170の分科会で報告と討論が行われました。 ここで強く印象づけられたのは、先進諸国では家族の変容に対応して速やかに法改正が実現すること、しかも制度内容は児童の権利条約の趣旨を明快に反映していることです。 わが国からは若林昌子氏(もと福岡家裁所長、明治大学教授、現首都大学東京法科大学院非常勤講師、 当法人養育費相談支援センター事業運営委員)が「日本の離婚調停の問題点と司法改革の時代に向けての挑戦」という題で、また数人の学者がそれぞれのテーマで報告を行いました。 国際家族法学会における若林昌子氏の講演要旨同氏は日本における家事調停制度の沿革と特色を紹介し、今日直面している問題とこれに対処する考え方をアメリカのミディエーション と対比しつつ要旨次のように論じました。 家事調停制度が特に子のある夫婦の紛争解決に重要な役割を果たしてきたのは事実であるが、1948年に制度が創設されて以来実施細則がなく、 基本的な改正もなされなかったので社会と当事者のニーズの変遷に対応することが難しくなり、調停の運営が担当者により区々である、権威的に過ぎるといった批判が起こってきた。 2004年に人事訴訟の管轄が地裁から家裁に移され、2007年にADR法が施行され家事調停は家裁の独占ではなくなり、かつて経験したことのない挑戦にさらされ変革を迫られている。 家事調停の特色は、裁判所の中に設置された制度であり、裁判官および二人の民間人である調停委員が担当することにある。 担当者は当事者が自ら適正妥当な合意に速やかに達するよう援助する役割を担っているが、これは技術を要することであり、 アメリカのミディエーション担当者と同様に専門的能力を高めることが必須である。合意を促進する方法として同席面接と当事者双方に交互に面接する個別面接がある。 それぞれ特色があるが、手続の公正さを担保するためにミディエーションにおけるように同席面接を原則とし、事案と場面によって個別面接を用いるなど適当に使い分けるべきである。 特に未成熟の子が絡む事件では、子の意思を尊重するために調査官の活用を図ること、また子の代理人制度を考慮することが必要と思われる。 また、時の経過とともに子が成長し、父母の生活も転居、失業、再婚等により変わり、共同監護が困難になることがあります。 自分たちで監護方法を変えても裁判所に報告しないことが多いので、監護に関する統計には正確な数字は表れてきません。 離婚時に取り決められた共同監護の形は変わってくるので、父母が各々二分の一に近い配分で監護を実施している家族の割合は全体の約10%に過ぎないと推定されています。 日本家族<社会と法>学会(2008.11東京)における養子制度の国際比較アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどではイギリスを除き成年養子も認められていますが、養子縁組の主たる目的は子の福祉です。 これらの国では一旦縁組が成立すると、子と実父母との関係が断絶する「完全養子縁組」を原則としている(例外的に実父母との縁が切れない養子縁組もある)ので、 ここでは断絶型の養子縁組について論じます。 想定される親子像としては、養親の年齢上限を決めている国はないが、養子より15歳以上年長であることを要求する国が多いです。 養子の上限年齢は多くの国で成人に達するまでとしています。 縁組に当たり父母の同意は必要とされますが、一旦同意すると撤回を認めない国がほとんどです。子の同意については、一定年齢以上の子につき必要とされるのが基本です。 わが国の特別養子制度わが国で、断絶型の特別養子制度が施行されたのは昭和63年で、平成20年は20周年に当たります。 この制度は恵まれない子を救う画期的なものとして喧伝され、当初は多数の申立てがありましたが、平成10年から16年までは全国で年間成立件数が400件台、 17年、18年には300件台で推移しています。 児童虐待の件数は増大し、児童施設は満杯で救うべき子は沢山いるはずですが、こんなに少ないのはなぜか。何が折角のこの制度の利用を阻んでいるのか。 家族<社会と法>学会がこの制度をテーマに取り上げた狙いはここにありました。 まず養子となる者の年齢が原則として6歳未満と適用の幅が極めて狭いことが挙げられますが、その他いろいろな問題点があることが分かってきました。 その一つとして父母の同意の問題があります。 家裁は申立てがあると、まず父母の同意の有無を確かめます。父母は、その時点で同意しても、家裁が養子縁組成立の審判をして確定するまで自由に撤回できます。 縁組を成立させるには、養親となる者と子が本当に親子としてなじめるか見究めるために一定の間の試験養育期間を設けることが要求され、調査も要するので、 父母が最初に同意してから審判確定までかなりの期間を要します。この間に父母の気持ちがふらつくことがあります。 もともと特別養子縁組を考えるのは、父母による養育が著しく困難または不適当な事情があって、施設に入所している子に親を与えようとして養育家庭を斡旋した場合がほとんどです。 こうした子は誰に対しても不信感を抱き、容易に心を開きません。ときには相手の愛情を試そうとして、わざと反抗的態度をとったりします。 養育者は必死になって子に気持ちを分からせようと努力し、子もようやくなじんできたころに突然父母が同意を撤回すると、この縁組は成立せず引き離されてしまいます。 同意撤回の理由が、父母自ら子を養育しようという確固たる意思を固め、その環境も整ったことにあるのならよいのですが、多くはそうではなく、 仮に子を引き取ってもすぐお手上げになったり虐待したりして、子はまた施設に舞い戻ることになりかねず、養育者も子も深く傷つきます。 特に子は生涯にわたる心の傷を負うことになるでしょう。 わが国の制度が縁組可能な範囲を狭め、父母の同意を厳格に要求するのは、親子の血縁関係を断絶することに強いこだわりがあるからのように思われます。 しかし、血縁関係とはそんなに絶対的なものでしょうか。 むしろ諸外国のように断絶型の養子縁組の門戸を広げ、実父母の恣意を制限することが子に真の幸せをもたらすのではないでしょうか。 子の意思の尊重児童憲章ができ、児童の権利条約が締結されるなど世界的に子の人権を尊重すべしとする声が高まっています。 子の人権を尊重するというのは単に子を保護の対象としてみるだけでなく、子を権利の主体としてみること、特に子に関係する事件についてはその意思を尊重し、 意見表明権を保証することとされます。 父母が紛争を始めると、双方とも子を味方につけようとしたり、押し付け合ったりで、子は紛争に巻き込まれます。 こうなると、父母はどちらも自分の利益を離れた立場で子を代表することができません。 こうした事態に対処するために諸外国では、子独自の「代理人」を選任することが考慮されるようになりました。 たとえばドイツでは手続保護人(Verfahrenspfleger)という制度ができ、裁判所が子の利益のために必要だと判断すると、子自身の立場に立って動き、 その意見を代弁しまたは表明できるよう図る職責を担う専門家の中から手続保護人を選任します。 登録しているのは法学者、弁護士、ソーシャルワーカー、教育学者、心理学者、教師などです。 しかし子の意思を知る、さらに子が意見を表明するというのは簡単なことではありません。 年齢にもよりますが子には初めからある確固とした意思があり、これを表明できないのは父母双方に遠慮しているからというわけではなく、 父母それぞれを愛していて父母が争うと身動きが取れずどうしてよいか分からなくなってしまうという状況にあることが多いからです。 この状況をときほぐし子の真のニーズを把握し、子にとっての最善の策を探るのはどの分野の専門家が担当するにせよ時間と労力と技術を要する大変な作業なのです。 |
|
【「ふぁみりお」46号の記事・その他】 |