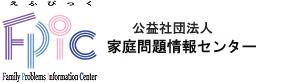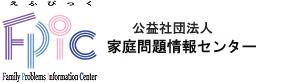1 子どもの幸せとは
子の処遇については親の権利を云々する前に子ども自身の幸せを考えるべきだということは現代の基本的な考え方で、どの立場からしても異論のないところでしょう。しかし父母双方とも自分が引き取る方が子がより幸せになると主張するとき、どう判断するかは難しい問題です。それぞれの言い分には多かれ少なかれ理由も粉飾もあり、一筋縄ではいきません。親子の人間関係、愛情などを把握するには専門的な調査や継続的な観察が必要な場合もあります。現在の状況だけでなく将来の予測を立てることも欠かせません。また判断者によって結論が大きく異なっては困ります。そこで何らかの判断基準が必要になります。アメリカのリンダ・エルロッド弁護士は子の親権(英米法では監護権と同じ)の帰属の変遷と子の立場について、アメリカの動向を次のように概説しています。
(1)揺れ動く判断基準
何世紀にも亘って子は父のもので、父母が離婚すれば当然父が親権者となった。
しかし男女平等の原則が普及するにつれてこれは揺らいできて、とくに子が幼い場合には直接世話をする母が優先すべきだとされる
ようになった(tender year presumption)。
1970年代になると父母は平等とされ、基準は「子の最善の利益」(the best interest of the child)とされた。
しかしこれは明確な概念ではなく個々の家庭の環境、親子関係などを考慮することが求められ、父母それぞれが優先することを主張し
訴訟が多発した。こうしたことがらを判断する専門的な訓練を受けていない裁判官は、自身の価値基準により判断するほかなく、
結論は区々となり混乱が生じた。
1980年代ごろから勝者、敗者の決定を避けるために、父母は離婚後も共同親権(joint custody)をもつとする法制が普及した。
しかし共同親権を適切に活用するためには父母に高度の協力関係が要求される。
それができない父母はかえって敵対心を煽られ争いが激化する。
時間の平等を徹底すると子は絶えず父母の間を右往左往させられて生活が不安定となり、
心に傷を負い成人後も引きずる恐れのあることが分かってきた。
1990年代ごろから、子の安定を重視しおおむね父母の別居以前に子が過ごした状態に合わせた生活をさせるという考え方
(approximation rule)が普及した。そしてこれを円滑に適用するために親は協力することとし具体的な親子交流の計画
(parenting plan)を立てる、話し合いをするとしても対立的構造でない手続で行う、
必要があればペアレンティング・コーディネーター(parenting coordinator) の援助を求めることができる、
といったことが現在の主流になっている。
(2)子の当事者としての位置
紛争の渦中にある父母は、子を思いやる余裕がなくなり子を巻き込んでしまう。
こうした高紛争家族にあっては、子は父母とは別の当事者としての立場を保障されなければならない。
すなわち、子は独自の意見を表明する権利をもち、子自身の代理人を選任することも考慮されるべきである。
問題の解決に当たっては、法律家のみならず、子の代理人やペアレンティング・コーディネーターなどとして
精神的な問題を扱うことのできる専門職の協力をえるべきである。
2 ハーグ条約の基本と目的
子の奪い合いが国境を越えて起こった場合、すなわち一方の親が他方の親の親権を侵害して国境を越えて子を移動
(連れ去りと留置を含む)し、残された親が返還を求める場合は極めて難しい問題となります。
子を取り戻すのは同じ国の中でさえ容易でないのに、他国に連れ去られた場合にはその国で訴えなければならないので
一般の親が行うことは困難で、弁護士を頼めば莫大な費用がかかります。
国際裁判管轄権と準拠法の問題(親権についての規定は国により異なる)もあり、
決着には当事者が同じ国内にいる場合より長期間かかります。子どもは日々成長を続ける存在であり、
不安定な状態が長く続くと心に傷を負い健全な成長を阻害される恐れがあり、最善の利益に反します。
そこで子の利益を守るために1980年にハーグ条約が採択されました。
その基本は、子が不法に国境を越えて移動された場合、迅速に移動される前に住んでいた常居所地(のある国)に返還する、
そのために国が力を貸すということです。子がいずれの親に育てられるのが相当かという親権に関する判断は
常居所地の国の裁判所に委ねることになります。
ハーグ条約は子を迅速に常居所地に返還することによりその子の最善の利益を図ることを目的としているのであって、
親の権利の回復や調整を図るものではありません。
したがって子の最善の利益を明記した「児童の権利に関する条約」(1989年に採択、日本は1994年に批准)とは矛盾しません。
さらに、ハーグ条約は子を移動してもすぐ戻されるから無駄となることを周知させることにより、
子の不法な移動を防止する効果をも狙っています。
親子が別れて暮らす場合、面会交流できることは子にとっても親にとっても大切です。
異なる国に住む親子の面会交流は難しいこともあるので、ハーグ条約ではこれを援助することも目指しています。
3 例外の場合
とはいえ現実のケースはさまざまで、直ちに返還することが子の不利益になりかねないケースはありえます。
そこでハーグ条約では原則の例外として、子の返還を命じない場合を規定しています。すなわち第13条によれば、
①子の返還を請求する者が移動の時点で現実に監護していなかった又は移動に同意していた場合、
②子を返還すれば心身に危害を加え又は許し難い状況に置く重大な危険のあることが証明された場合、
③意見を述べられる程度に成熟している子が異議を述べた場合、当局は返還を命じる義務を負わないことになっています。
②については、子が虐待される恐れのある場合が典型的ですが、何が虐待に当たるかという問題があります。
最も難しいのは③の場合です。意見を述べられる程度に成熟しているといっても、
子は親に両面感情(好きでもあり嫌いでもあるという相反する感情)をもっていることが多いし、気持ちは揺れ動きます。
双方の親への愛情や忠誠心が絡み合い、率直に言えないこともあります。
このような状態に置かれた子の声を聴き、真のニーズを把握するには慎重な対応を要します。
4 オーストラリアでの実績
オーストラリアでは、ハーグ条約の批准に伴い国内法を整備し、裁判所が他国から移動されてきた子の返還請求事件を審理しています。
2003年に国が受理した件数は43件で、自発的返還、却下、取下げなどを除き裁判所が審理した件数は25件です。
審理の結果は、返還を命令した件数16件、返還を拒否した件数7件です。面会交流が命令又は合意された件数は3件あります。
審理期間の平均は裁判により返還を命じた場合163日、返還を拒否した場合118日となっています。
手続は事実審裁判官の単独審、家庭裁判所における合議審、高等裁判所による合議審(最終審)と進みます。
裁判所の審理に要した平均期間を1999年と2003年で対比すると、返還命令を発した場合は91日から131日に増加、
返還を拒否した場合は220日から118日に減少しています。
これらの数字を見ると審理にはかなりの時間をかけていること
(第11条によれば6週間以内に決定しないときは説明を求められることがある)、
とくに返還命令を発する場合には慎重に取り組むようになってきたことが窺われます。
5 カービー判事の意見
オーストラリア高等裁判所のマイケル・カービー判事は、母親が外国から子を連れて戻った5件(うち4件に自身が関与)を紹介しています。
父親からの返還請求に対する母親の抗弁はそれぞれ、子が異議を述べている、
子は自閉症で常居所地には対応できる医療機関がない、子を返させられれば母は自殺するので子は耐え難い状況に陥る、などです。
一審は返還を拒否し、家庭裁判所ではこれを覆して返還を命じていますが、
最終的に高裁は5件とも返還を拒否するか又は家庭裁判所に差し戻しました。
カービー判事の「例外は狭くかつ厳格に解釈し、原則に従って迅速に返還すべきである」という意見は少数に止まり、
通らなかったとのことです。
同判事は、「多くの移民を抱えるオーストラリアはこの条約を多用する国であり、その裁判所が条約の規定に従わないならば、
他国の裁判所も同じような対応をすることになり、この条約は骨抜きになる。
結局子を連れ去った者が勝ち、子の利益が害されることになる」と批判しています。
6 おわりに
親子の関係は微妙であり、子どもは大人が考える以上に分かっていることもある半面、繊細で傷つきやすい存在で、
真のニーズを把握するには時間がかかることもあるでしょう。カービー判事のように、
迅速に返還するという原則にあくまで忠実にせよとは必ずしも言えないかもしれません。
とにかくエルロッド弁護士が論じているとおり、子の立場を尊重し安定を図ること、
そのために人間関係や心理に詳しい専門職の協力をえることが必要と思われます。
裁判官が判断する場合にも、法律一点張りでない配慮が求められるでしょう。
|